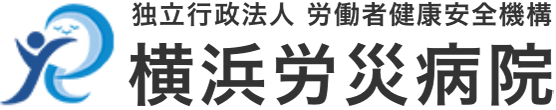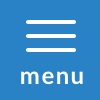輸血部
診療科からのお知らせ/コラム
新着情報はありません。
診療科紹介
輸血療法は国策に基づいて実施される、献血で得られた血液を原料とする治療法であり、資源材料となる血液が有限で、善意による寄付であることから、適正な使用が求められています。また、輸血療法は最も簡便な臓器移植であり、完全に安全ではない、本質的な危険性を排除できない治療法でもあるため、最低限の使用と共に安全性の確保が求められています。
採血基準の厳格化、問診の細項目化、免疫学的検査や遺伝子増幅検査による血液の感染スクリーニング、初流血除去、血液製剤中に混在する白血球の保存前除去、放射線照射による白血球不活化、一定の保存期間後の製剤出荷、遡及調査の実施等により、近年、血液製剤の安全性は格段に向上しました。
しかしながら、以前より指摘されているウインドウ期の感染症伝播やパルボウイルス、EBウイルス、ヘルペスウイルス感染の問題だけではなく、プリオンや西ナイルウイルス、SARSを起こすコロナウイルス等の血液を介して感染する恐れのある新たな病原体が発見されたり、インフルエンザ感染者の献血により作成された血液製剤が回収されるという事例がありました。2013年には輸血によるHIVおよびHCV感染例が報告されるとともに、日本で初めて献血血液よりシャーガス病感染血が発見されました。2014年夏には蚊によって媒介されるデング熱が日本でも稀ではなく発生していることが確認されました。2015年には免疫抑制患者での輸血によるHEV慢性感染が話題となり、さらに2016年初頭には、ブラジルで、妊婦のジカ熱感染により胎児や新生児の小頭症発症リスクが高まっていること、このウイルスが蚊によって媒介されること、輸血による感染症例があることが報告されました。近年では、輸血によるHEV感染の増加が指摘されています。
血液製剤の安全確保のための方策は常に改良が加えられており、2014年8月1日からは、プール血清ではなく献血血液全例での個別核酸増幅検査が実施されています。
血液中には感染性を有する未知のものが、まだまだ含まれていると推測されます。輸血療法では、感染症以外にも免疫反応に基づく副作用や合併症が生じる危険性があり、まれに致命的な転帰をとることもあります。
当院が開院以来1件として重大な輸血事故がないことは、患者さんを含め輸血に携わるもの全ての努力の賜物ですが、製剤の取り違えによる輸血事故が新聞等で報道されることもまれではなく、輸血療法、血液製剤が本来的に有する危険性を改めて認識し、より安全な輸血療法を推進することが必要です。少子高齢化や人口の減少、変異型クロイツフェルトヤコブ病(vCJD)に関連した献血基準の見直しなどによる献血者数の減少による献血量の減少に対応し、血液製剤の国内自給を達成するために、より一層の適正使用の推進が求められています。2020年にはSARS-CoV-2によるパンデミックが発生し、献血血液不足が話題となりました。輸血をめぐる状況についての詳細は、厚生労働省による血液事業報告や日本赤十字社による輸血情報、Haemovigilance by JRCをご覧頂ければと思います。
当院では厚生労働省の「血液製剤の使用指針」および「輸血療法の実施に関する指針」を遵守し、輸血に関する業務を輸血部で一元的に管理すると共に、定期的に輸血療法委員会を開催して安全かつ適正な輸血療法の施行のために努力しております。
当院は2006年4月より輸血管理料Ⅱを算定していましたが、輸血部でのアルブミン製剤一元管理を行い、2018年10月より輸血管理料Ⅰを算定しています。また2018年2月には日本輸血・細胞治療学会に輸血機能評価認定制度(I&A制度)および日本適合性認定協会によるISO15189(臨床検査室の認定:品質と能力に関する特定要求事項)の認証を受けています。
診療内容
輸血関連検査業務
輸血に必要な検査の実施(血液型検査、交差適合試験、不規則抗体のスクリーニングや同定など)と報告、適合血選択のコンサルテーション
輸血製剤の管理
血液センターへの血液製剤の発注、血液製剤の管理および払い出し、輸血製剤による副作用報告の収集と分析、血液製剤使用実績の統計作成、日本赤十字社による遡及調査等への協力
採血業務
自己血輸血のための貯血業務と貯血自己血の管理、末梢血造血幹細胞採取の介助と採取幹細胞液の管理、瀉血の介助
診療体制
平澤晃副院長(輸血・細胞治療学会認定医)、中央検査部・中村和之部長の協力の下、佐藤忠嗣輸血部長および臨床検査科部長兼任と5人の技師で担当しています。うち2名は認定輸血検査技師を取得しています。時間外の輸血業務は中央検査部当直技師が担当し(総数31人)、輸血業務担当者が支援する体制を取っています。
スタッフ紹介
-
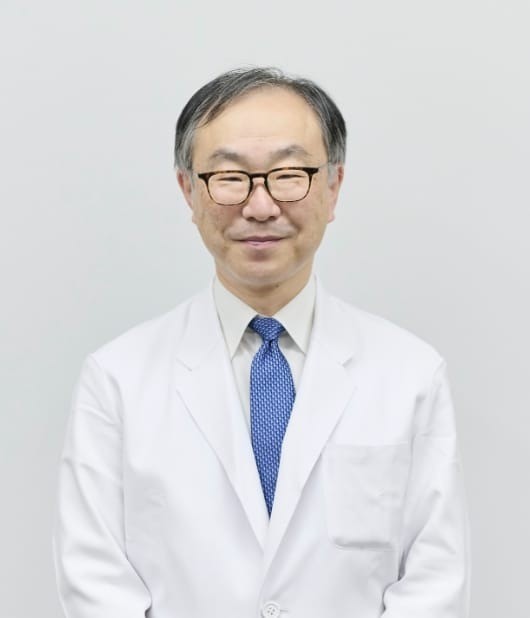
副院長 内科部長 輸血部長
平澤 晃/ ひらさわ あきら
卒業年次 昭和60年 専門分野 内科学、血液病学、輸血学、感染制御 学会専門医・認定医:
日本内科学会認定総合内科専門医・指導医、日本血液学会認定血液専門医・指導医、日本輸血・細胞治療学会認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、インフェクションコントロールドクター(日本感染症学会)、日本医師会認定産業医、千葉大学医学部臨床教授
-
医師
佐藤 忠嗣/ さとう ただつぐ
卒業年次 昭和60年 専門分野 内科学、血液病学、輸血学 学会専門医・認定医:
日本内科学会認定総合内科専門医・指導医、日本血液学会認定血液専門医・指導医、日本輸血・細胞治療学会認定医
診療実績
臨床実績
血液製剤取り扱い実績(各年1月〜12月:年度は4月より3月)
| 輸血実施患者数 | 2018年 | H.30年 | R.1(2019)年 | R.2(2020)年 | ||||
| 総数 | 1,028 | 931 | 819 | 843 | ||||
| 同種血のみ | 814 | 713 | 633 | 736 | ||||
| 自己血のみ(貯血式使用) | 193 | 196 | 174 | 95 | ||||
| 同種血・自己血併用 | 21 | 22 | 12 | 12 | ||||
| 製剤別使用量 | 2018年 | H.30年 | R.1(2019)年 | R.1(2020)年 | ||||
| 単位 | 本数 | 単位 | 本数 | 単位 | 本数 | 単位 | 本数 | |
| 全血製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤血球製剤 | 6,978 | 3,503 | 6,840 | 3,424 | 6,566 | 3,289 | 5566 | 2785 |
| 血小板製剤 | 7,185 | 597 | 6,540 | 541 | 4,945 | 440 | 5645 | 549 |
| 新鮮凍結血漿 | 3000.00 | 1,200 | 2606.00 | 1,081 | 2172.00 | 906 | 1284.00 | 577 |
| 貯血式自己血 | 562 | 289 | 526 | 263 | 465 | 233 | 278 | 140 |
| アルブミン (g) | 19,150 | 19,750 | 15,312.5 | 16537.5 | ||||
| FFP/MAP比 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | ||||
| アルブミン/MAP比 | 0.85 | 0.86 | 0.73 | 0.94 | ||||
-
診療科・部門のご案内
-
診療科
- 総合診療部(休止中)
- 糖尿病内科・内分泌内科・代謝内科
- 血液内科
- 腎臓内科
- リウマチ科・膠原病内科 (リウマチ・膠原病センター)
- 腫瘍内科
- 緩和支持治療科
- 心療内科・精神科
- 脳神経内科
- 呼吸器内科
- 呼吸器外科
- 消化器内科
- 循環器内科
- 小児科・新生児内科・小児外科
- 外科・消化器外科
- 乳腺外科
- 整形外科
- 脊椎脊髄外科
- 手・末梢神経外科
- 人工関節外科
- 形成外科
- 脳神経外科
- 脳神経血管内治療科
- 心臓血管外科
- 皮膚科
- 産科・分娩部
- 婦人科
- 女性ヘルスケア部
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- リハビリテーション科
- 放射線診断科・放射線IVR科・放射線治療科
- 麻酔科
- 泌尿器科
- 救急科・救急災害医療部
- 歯科口腔外科・口腔内科
-
部門
-
センター